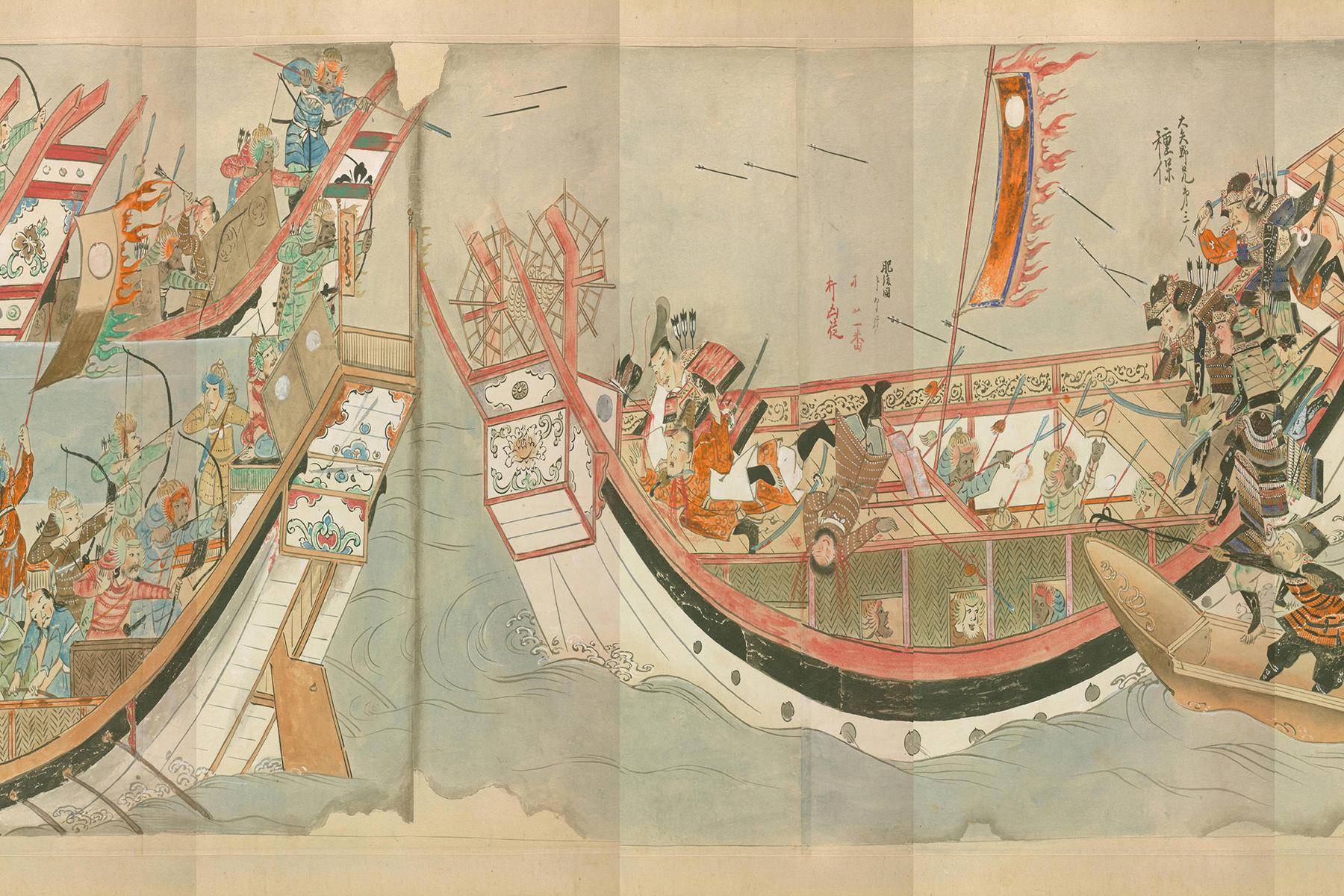【田舎庵】伝統を守り、革新を続ける日本一の鰻職人
創業90年の田舎庵(いなかあん)4代目・緒方大(おがた だい)さんにインタビュー。日本を代表する鰻料理と、日本一と称されるその技に迫ります。
日本を代表する創業90年の老舗
北九州市小倉。居酒屋やバー、スナックが並ぶにぎやかな繁華街の中で、落ち着いた日本風情漂う店がある。軒上にある木彫りの看板には「田舎庵」の文字。清々しい真っ白な麻の暖簾をくぐり格子の引き戸を開けるとたちまち、タレを焦がした香ばしい匂いが鼻孔をくすぐる。
昭和元年に創業した鰻料理専門店「田舎庵」は現在、3代目の緒方弘さんから引き継ぎ、長男・大さんが切り盛りしている。先代の緒方弘さんは鰻に関するその知識量と技量から「鰻の神様」と呼ばれ、日本全国のメディアで取り上げられ、海外からも招へいされるほどの名人だ。
この日、テレビ撮影の立ち合いで不在にしていた弘さんに代わって案内してくれたのは4代目を受け継ぐ大さん。挨拶もそこそこに「まずは見てください」と通された調理場には、まるまると太った立派な鰻が桶の中で勢いよくうねうねと動いていた。
そのうち一尾をつかまえ、目打ち(※)で固定すると胸びれのあたりに包丁を入れ、ぐーっと腹を割いていく。きれいに開いた身から肝を取り除き、骨にそって刃を滑らせるとあっという間に身と骨、内臓に分けられた。その間、わずか数十秒。早くも職人技に魅了される。 この業界では「串打ち三年、割き八年、焼きは一生」という言葉がある。一人前になるまでにそれほど修練が必要というたとえだ。
「実際には毎日練習すれば3年ほどで串打ちと割きはできるようになります。私は包丁を持って13年経った今も、これで一人前だと思うことはありませんけれどね」と大さん。朗らかな笑顔で話しながらも目の前の鰻を手際よく捌いていく。均等な長さに切った身を並べ、長さ40センチほどの金串を12本刺すと「それでは焼きますね」と炭の前に立った。
蒲焼きの極意「鰻に火を食わせる」
日本全国数多とある鰻料理店の中で「田舎庵が日本一」と称する食通が多いのはその独特な焼き方にある。
大さんは扇状に金串を刺した鰻を右へ左へとリズミカルに折り曲げながら炭火にかざす。鰻に焼き目がつくと途中で冷水をかけ、皮の部分に金串をぶすぶすと刺しながら焼き上げていく。この「折り返しながら焼く」「途中で冷水をかける」「金串を刺す」という3つの工程は田舎庵独自の方法で、他店では類を見ない。
「鰻の皮は2層になっていて内側にゼラチン質があるんです。これがグニャっとした食感になる原因ですね。鰻を折り曲げると皮に亀裂が入り、このゼラチン質が溶け出していきます。こうして溶け出た脂を鰻全体に回しながらじっくりと焼いていく。すると、鰻の旨味をすべて生かすことができるんです」
途中で冷水をかける理由は何か。
「私たちの店では鰻が炭になる直前まで約30分かけて徹底的に焼き上げます。時間がかかりますから、その分、身の薄い部分が焦げないよう冷水で温度を下げながら焼くんです。そうすることで身の厚い部分まで均等に火を通すことができます」
こうして時間をかけて焼き上げる際、身が崩れないように金串で皮を刺しながら形を整えているという。
焼き方だけでなく、タレのかけ方にも独自の技がある。一般的には焼き上げた鰻をタレに浸し、もう一度焼き台にのせる。しかし、田舎庵では焼き台にのせたまま上からタレをかける。
「理由は二つあります。タレをくぐらせて鰻の温度が下がるのを避けるため。もう一つは、鰻に煙を浴びせるためです。タレをかけると落ちた脂が炭で焦げ、煙が一気に上ります。その煙がまるで燻製のように鰻を包みこむことで香りが立ち、いっそう美味しくなるんです」
3つの焼き工程と仕上げのタレ。独自の技で臭みや皮の食感を取り除き、鰻の旨さだけを残した日本一の蒲焼きが完成した。
江戸時代から数百年続く風習
背中から開いて焼いた後に蒸す「関東風」、腹から開いて焼き上げる「関西風」など調理法に地域差があるのも面白いところ。関東では武士文化の影響が強く、「腹を切る(切腹)を避けて背開きにした」という説もあるが、実際には関東の土壌で育った鰻の泥臭さを落とすために蒸す工程を加えた結果、「身が崩れにくいから背開きになった」というのが定説だ。
鰻の蒲焼きが広がったのは江戸時代中期から後期。その背景には調味料の発展が影響している。醤油の香ばしさとみりんの甘さが混ざり合ったタレは江戸庶民を魅了し、蒲焼きの店が増えた。さらに、鰻の人気を煽ったのは「エレキテル」を発明した蘭学者・平賀源内(ひらが げんない)である。
もともと、鰻は他の魚と同様、脂がのった冬が旬だとされていた。夏場の売れ行きに悩んでいた鰻屋から相談を受けた平賀源内が、入口に「本日土用の丑の日(ほんじつ どようのうしのひ)」と張り紙をしたことで人目を引き、「土用の丑の日に栄養価の高い鰻を食べれば暑い夏も乗り切れる」という風習が広まった。
実際に、栄養学的な観点からも鰻は身体の抵抗力を高めるビタミンAや疲労回復に役立つビタミンB1を豊富に含む。江戸時代の蘭学者が用いた方便は栄養学のエビデンスに裏付けられ、数百年経った今も「土用の丑の日には鰻を食べる」という風習を残している。
天然に負けない鰻をつくる
鰻は300年以上続く食文化だが、その伝統を支える業界は厳しい現実に直面している。日本の天然鰻の漁獲量はここ50年で2000トン以上も減少。今や流通している99%が養殖鰻だ。日本で鰻の養殖が始まったのは明治12年(1879年)のこと。昭和30年前後(1955年前後)までは天然鰻が豊富だったが、その頃から漁獲量が激減し、養殖業がさかんになっていった。
今や天然鰻は高級品となり、鰻の幼魚・シラスは1キロ300万円まで高騰している。そんな中、田舎庵では多くの人に美味しい鰻を食べてもらうために、質の高い鰻を安定供給できる養鰻家や卸業者と関係を築いている。
仕入れ先の一つは小倉から車で1時間弱、行橋市蓑島(ゆくはしし みのしま)にある漁場だ。ここで20年近く卸業を営んでいる森林保以(もりばやし やすじ)さんは「鰻は育った場所で味が違う」と語る。
「清流で育った鰻は美味しいと思われがちですが、水がきれいな場所だと藻ばかり食べているので淡泊な味になるんです。ちょっと濁ったような河口域ではアサリやマテ貝、エビやカニなど海の生き物が豊富ですから、味わい深い鰻が穫れます」
この漁場では天然鰻を扱っているが、天然に負けないくらい美味しい養殖鰻もある。もう一つの仕入れ先、鹿児島県種子島にある養鰻場では水槽ではなく池を掘って、水温をコントールすることなく自然に近い環境で飼育している。そんな場所で育った鰻は身がしっかりとして、旨味があり天然に負けない味なのだという。
「よく年配の方から『昔の鰻はうまかった』という話を聞くんです。でも、天然鰻が減ったから美味しい鰻は食べられないなんて決まったわけではありません。2014年に、父や養鰻家の方々と日本一の鰻をつくるプロジェクトを立ち上げました。天然よりも美味しい養殖鰻の飼育に挑んでいるところです」(緒方大さん)
世界へ飛び立つ鰻職人
緒方さん親子は年に一度、イタリア北部の街コマッキオから招待状が届く。鰻の名産地であるコマッキオでは、毎年9月下旬から10月上旬にかけて街をあげて鰻祭りが開催されるのだ。
数年前、知人の紹介で訪れて以来、毎年足を運んで日本の鰻料理を振る舞っているうちに、ついには市長自ら出迎えてくれるまでになった。
「ある文献によると古代ギリシア・ローマでも鰻が食べられていたそうで、それが日本の蒲焼きとよく似ているんです。背中から割いて魚醤とハチミツと胡椒、ワインとハーブで味付けをしていた、と。魚醤は醤油、ハチミツの甘みとワインのアルコールはみりん、ハーブは山椒ですね。そういった背景を考えるとヨーロッパでは蒲焼きの味に親しみがあるのかもしれません」
近年はコロナ禍で海外渡航が難しいが、以前はイタリア・コマッキオからも「料理教室をして欲しい」とオファーが届いていたという。今後、海外渡航が解禁されればその活躍はますます広がっていくだろう。
300年の歴史を持つ日本の伝統的な食文化を田舎庵は独自のスタイルに昇華させ、その舞台を世界へと広げてさらなる歴史を紡いでいる。
プロフィール
緒方大(Dai Ogata)
「田舎庵」4代目店主。曾祖父が創業した店を受け継ぎ、海外に向けた日本料理・鰻の情報発信にも力を注ぐ。
田舎庵
北九州市小倉北区鍛冶町1-1-13
093-551-0851
https://www.inakaan.com/
Interview and text:Sakiko Kobayashi(Chikara)
Translation:Aaron Schwarz
Photography:Kazuhiro Kaku
Project Direction:Chikara